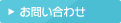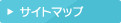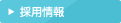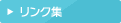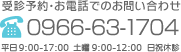7月20日~21日、新潟水俣病の現地調査に参加しました。今回初めて参加させていただきましたが、新潟でおきた水俣病の歴史について学ぶ、貴重な機会となりました。全体の案内は阿賀野患者会の酢山さんにしていただきました。
まず訪れたのは、水俣病の資料館、「県立環境と人間のふれあい館」です。この施設は、新潟水俣病の歴史と教訓を後世に伝えるために設立され、環境と人間の関わりをテーマにした学習・交流の場となっています。
熊本の水俣病が公式に発見されたのは1956年(昭和31年)。その9年後、1965年(昭和40年)5月31日新潟大学の椿・植木教授が原因不明の水銀中毒患者が阿賀野川下流域に散発と新潟県に報告したことで新潟水俣病の公式確認となりました。熊本の水俣病と同様に、食物連鎖を通して魚に取りこまれ、濃縮されていき、そのことを知らずに川魚を食べたことで新潟水俣病が発生していったこと、阿賀野川でとれる魚の種類や当時の漁の方法、加害企業の情報、病像、救済制度、差別や偏見に苦しんだ患者の歴史など、工夫された展示で紹介されていました。
加害企業である昭和電工鹿瀬工場の跡地にも足を運びました。水資源が豊富な阿賀町(旧鹿瀬町)には阿賀野川の鹿瀬発電所の電力が利用でき、周辺では石灰石も採掘されていました。鹿瀬工場では酢酸や酢酸ビニルなどの原材料となるアセトアルデヒドを生産しており、その工程でメチル水銀が副生されました。山の中の工場ですが、関連する仕事に従事していた人は3000人程、工場を中心に一つの町が形成されていたと言います。水俣が「チッソ城下町」と呼ばれるのと同様に、鹿瀬も鹿瀬工場が地域住民にとって大きな存在であったことがうかがえます。写真の建物は新潟水俣病の裁判の報道にたびに登場する施設とのことで、現在は子会社の新潟昭和株式会社が使用しているそうです。
会社から少し離れたところに工場排水の排水口があります。排水口から工場排水を阿賀野川へ放流、アセトアルデヒドの生産がおこなわれていた当時は、異臭が漂っていて鼻をつまんで歩くほどだったといいます。周辺の井戸水を沸かすと臭いにおいがしていたそうです。1966年(昭和41年)この排水口の水苔から461.8ppmのメチル水銀が検出されました。排水口より上流ではメチル水銀が検出されなかったことから鹿瀬工場が水俣病の原因であることが明らかになりました。
こちらの排水口にはお知らせの看板も何もありません。案内の方がいなければ見過ごしてしまいそうなところです。
現在、ノーモア訴訟で闘っておられる原告の方々から、お話を伺う機会がありました。豊かな阿賀野川で幼いころから遊び、魚を獲り、水を汲み、川と共に暮らしてこられた患者さん、橋ができる以前は陸の孤島のような環境で、阿賀野川の魚が唯一のたんぱく源だったと話しておられました。海に近い地域で育った自分には、川魚を食べる文化が不思議に感じられましたが、お話を聞いて川と共に生きてこられた方々の暮らしを理解することができました。
原告のみなさんは高齢になられており、身体の痛みや持病を抱えながら、裁判を続けておられます。裁判にかかわることで家族から反対され、長く会えていない状況が続いている方もいます。「解決したら娘とハグがしたい」と話される姿が深く胸に残りました。水俣病を理由とした差別や偏見は今もなお続いており、悲しい思いを抱える患者さんもいらっしゃいます。一刻も早い解決が望まれます。自分の足で現地を訪れ、見て、聞いて、感じることの大切さを改めて実感しました。機会があれば他の職員にもぜひ参加してもらいたいと思いながら帰路につきました。